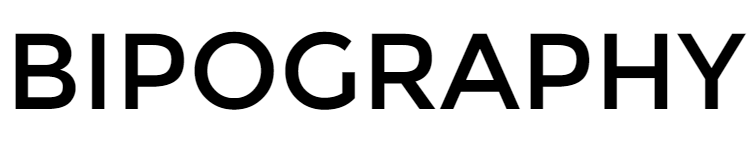躁状態の「動けない」と鬱状態の「動けない」
動けない、何も出来ないと思っている時でも、鬱の時もあれば躁の時もある。一概にこうであれば一方であるとは言えないが、私の見分け方はこうだ。Read more
ちょっとした気分転換やリラックスのためにしている4つのこと
自分なりにちょっとした気分転換やリラックスのためにしていることを書き出してみました。Read more
周りの人の言葉に敏感になり、思い煩ってしまうこともあるけれど
調子の悪いときは、他人や家族の些細な言動に過剰に反応してしまいます。考え込むときは、風呂にも入れなくて、翌日にシャワーを浴びる始末です。病気と診断されて、約10年。今の所、解決策は、寝逃げするくらいです!
自分だけ何もできず、世界から取り残されたような気持ちになった時は
コラムやエッセイ,うつ状態の時の過ごし方,病気と生きる・向き合う,対策
世の中、自分以外がすごく見えたり、「自分は何も成せない」みたいな感覚が来たり、とにかく自分以外の世の中がキラキラ輝いて見えて、Read more
大災害や大事故の発生といった社会情勢の変化を目にすることも躁転のきっかけに
躁うつの切り替わり周期やトリガー,対策,症状,躁状態の予防策
新たな躁転のきっかけに気づいたときは、予防策を考えて日記にメモっておくことにしています。最近気づいたのですが、Read more
日記を振り返り、今の自分がどの状態にいるのか考える
その日の気分と行ったことを日記に記しています。過去の日記を読み返して、現在の状態がどこに当てはまるのかを考えることで、躁状態の未然防止に役立てています。
睡眠薬のおかげで寝つきは良くなったけど、躁の時は未だに思うようにならないことも
小学生の時から入眠困難でした。14年前からサイレース(フルニトラゼパム)を飲んでいます。躁の時はなかなか眠れなかったり早期覚醒したりしてしまいますが。
気分を数値化して記録したり、刺激を少なくしたりして、躁の未然防止を図る
躁状態の予防策として、気分を0から10で記録することを続けています。0〜2:うつ、3〜4:寛解、5〜10:躁、というようにしています。Read more
ベッドから起き上がれない時は、歯ブラシなどの日用品を枕元に置いておく
体が重く、動くことが難しくなることが時々あります。全く動けない時は、もう寝返りを打つこともできませんが、Read more
6つの人格気質それぞれにおけるセルフケア方法を学び、実生活で役立てた
人間の性格や気質といったものを分類した「6つの人格気質」という考え方が役に立っています。循環気質、粘着気質、Read more
鬱の時は食事や入浴などのタスクを細分化して、些細なことでも出来たら「よし」と確認する
鬱のときは「いつも」どおりという概念を捨てたいです。毎回「いつもと同じように出来ない」とか「いつもの自分とはちがう」といったRead more
モヤモヤの正体がわからない時にマインドマップを書いてきた私が感じること
全般的な対策,コラムやエッセイ,病気と生きる・向き合う,対策
モヤモヤは毎日やってくる。
それは日常のちょっとした違和感だったりRead more
ストレスをなるべく感じずにできる散財防止法
買いたいものが次々に浮かんできたり、洋服や雑貨を欲しくなったりするのがいつものパターン。ちょっと気分がRead more
躁に傾くと、視覚と聴覚が過剰に働く一方、味覚・嗅覚・触覚がおざなりに
躁うつの切り替わり周期やトリガー,対策,症状,躁状態の症状,躁状態の予防策
調子が悪い時は、たいてい五感のバランスが崩れている。わたしの場合、視覚と聴覚がやけに過剰に働いて、味覚・嗅覚・触覚がおざなりにRead more
デジタル時計を脳内でアナログ表示に変換することで、時間の重みを実感でき、本当の過集中防止に
デジタル時計が苦手なことに気がついた。過集中防止のために作業時間を決めても、デジタル時計だと時間がただの数字の羅列に見えてRead more
太陽の光を感じ、庭の草花に触れたりすることで、少しずつ回復させる
私なりの回復方法は、自然に触れてみることです。
落ち込みがひどいとき
- 窓辺で楽な姿勢になって太陽の光や風を感じる。空を見る。
- ごろ寝しながらでも動かせるところがあれば、ストレッチする。
鬱を未然に防ぐため、スマホのアラームで休憩を促し、過集中を防止
仕事で作業に集中しすぎて、それが続くことで疲れて鬱状態になってしまう、ということがこれまで何度もあったので、あらかじめRead more
土曜日の日中は予定を入れないようにして、体力回復に努める
週5日フルタイム(8時間)で働いています。毎日ヘトヘトで鬱転や躁転しないように、そして身体も壊さないように自分をいたわりながら、細々と生活しています。Read more